お役立ちコラム
法律の改正や新設に関する情報について、制度の内容やデメリット、リスクなどを簡単にまとめてご紹介しています。
2025年10月17日:共同親権
親権とは
親権とは、親が子を監護教育したり(身上監護)、子の財産を管理したり(財産管理)する権利・義務です。
これまでは、離婚後には単独親権となっていましたが、今後、共同親権を選択することができます。(婚姻中は当然に共同親権です。)
改正民法818条1項は、「親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。」と定めており、子供に対して親の好きなことができる、という権利ではありません。
また、改正民法817条の12第1項は、親の責務として、「父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。」としており、子供の人格を尊重する義務、年齢や発達の程度に即して配慮する義務、自分と同じレベルの生活を維持できるようにする義務があることも定めています。
なお、共同親権部分の家族法改正は、2026年5月24日までの施行が予定されています。
Q1:私は子供と同居している親(同居親)です。共同親権になったら、子供と別居している親(別居親)の言うことをなんでも聞かなければいけないのでしょうか?
A1:
①監護及び教育に関する日常の行為や②子の利益のため急迫の事情があることは、同居親が単独でも行えます。
①の具体例は、重大な影響を与えない医療行為の決定、習い事の選択、短時間のアルバイト、短期間の旅行などです。
②の具体例は、緊急の必要がある手術行為、期限が迫っている中学校の入学手続き、DVや虐待から避難するための転居などです。
他方、①や②のような事情のない、就業許可、進学のための在学契約、医療行為等を単独で行うことはできません。(ただし、家庭裁判所が親権行使者を指定している場合は別です。)
また、預金口座の開設等の財産管理に関する行為、子の氏の変更等の身分行為の代理行為は両方の親が一緒に行う必要があります。
Q2:私は別居親です。共同親権になったら、子供との面会の回数を増やしたり、養育費を減額できたりしますか?
A2:
共同親権からただちに面会の回数を増やしたり、養育費の額を減額できる、ということにはなりません。
面会のルール決めは面会交流調停、養育費の額は養育費減額調停を申し立てる必要があります。
Q3:私は別居親です。共同親権になったら、子供との面会の回数を増やしたり、養育費を減額できたりしますか?
A3:
同居親と別居親の意見が対立している場合、裁判所で審判や訴訟によって、単独親権とできる可能性があります。
改正民法819条7項前段は「裁判所は、…父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。」としています。原則的に共同親権とする、というような規定はありません。
加えて、同項後段は、「この場合において、次の各号のいずれかに該当するとき③その他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」(①②③は筆者加筆)としています。そのため、①過去に別居親が子供を虐待していたり、②過去に別居親が同居親に対して暴力(精神的・経済的・性的暴力を含む)を行っていたり、③①や②に直接あたらなくとも同じくらいの事情があって子供の利益を損なうような場合には、単独親権になります。
ただし、まだ法律が施行されていないので、どの程度の虐待や暴力によって裁判所が単独親権とするのかは未知数であり(たとえば、1回だけ、軽度の暴力があったという程度では、単独親権とならない可能性は十分あります。)、裁判所の判断の蓄積を待つ必要があります。
過去の話題
最新のコラム記事
2025年8月13日:弁護士会照会
2025年4月14日:家族法改正
2024年4月1日:遺留分侵害請求権
2024年1月6日:2024年4月から相続登記が義務化されます

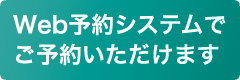
 このページの先頭へ
このページの先頭へ